プログラミングClojureにおける「データ」とは何か
プログラミングClojureは僕が読んだ二冊目のClojureの本で、 Clojureがどんな機能を備えているのか、どんなパラダイムなのかを 教えてくれるとても良い本。
読み終わった今でも時々、「あそこどう書いてたっけな」と気になってはすぐに読み返してしまう。
しかしながら、何度読んでも"具体的なオブジェクト"と"データ"という記述の違いが解らなかった。 その後、ひとりで悩んだり、人に相談してようやく理解できた。
この記事ではその理解をなんとか噛み砕いて説明しようと思う。
「データ」
どんなワークフローでプログラムを組んでいくのがよいか
プログラミングClojureではそれについて説明している箇所がある。 誰もが気になるところだ。文法や言語の機能が解ったところで、「実際どうやるの?」が解らなければ勇気をもって実装に踏み出せないものだ。
例えばこんな文章で説明されている。
Clojureでの設計の肝は、いつでもどこでも具体的なオブジェクトで溢れさせるのではなく、データそのものについて考えることだ。
引用元: 10.1 Clojurebreaker ゲームのスコアの計算 p.222
これが解らなかった
「データそのもの」とはなんだろうか。 具体的なオブジェクトとの違いは何だ?
さらにClojureプログラミングの原則として下記のようなことが書いてある。
・領域特有の具体物を持ち込まない(データはデータとして扱う)。
引用元: 10.1 Clojurebreaker ゲームのスコアの計算 p.224
これも解らなかった
「データはデータ」? データは具体物ではないのか? では何なんだ?
何が難しいのか
- 具体的なオブジェクト/具体物
- データ
この違いが解っていないから混乱する。もう一度文章をよく睨んでみよう。
Clojureでの設計の肝は、いつでもどこでも具体的なオブジェクトで溢れさせるのではなく、データそのものについて考えることだ。
データそのものについて考える。 それは具体的な何かの概念について考えることになるだろう。
そう思った。というか、そう連想した。
なので
データそのものについて考える=具体的なオブジェクトを設計する
ではないの?
・領域特有の具体物を持ち込まない(データはデータとして扱う)。
領域特有の具体物を持ち込まないプログラミング、というのが想像できなかった。
データが具体的でないのなら、いったいどんな形をしているのか、まったく解らない。 データは「扱われる」のだから何らかの意味で具体的になっているはずだろう。
教えてもらった
ずっと考えていても解決する兆しが無いので、直接訳者の方に質問してみた。
解ったこと
頂いた回答をもとにまとめると。。。。
具体物
{ :name "津島善子" :blood-type O :birth-day [Jul 13] }
データ
{ :name "津島善子" :blood-type O :birth-day [Jul 13] }
!?!?!?
同じっ!?
記法は同じ!!
しかし意味が異なる!!
どちらも同じMapだが、
「どう捉えるか」という解釈が問題。
それは確かに人を表す情報かもしれないけど、 それはいったん忘れて Map (key-value pairs) という データ として関数を適用しよう。
再咀嚼
Clojureでの設計の肝は、いつでもどこでも具体的なオブジェクトで溢れさせるのではなく、データそのものについて考えることだ。
・領域特有の具体物を持ち込まない(データはデータとして扱う)。
これらは何を言っているか。
対象の具体的な意味は忘れて、Map, Seq, Vectorとしてデータを変換するようなAPIを設計しよう、ということだ。
そして幸いにも clojure.core にそういった関数が膨大にある。
それを使えばいいじゃないか。
そう、それが再利用性ということ。
必要であれば自分で少し拡張しないといけないかもしれない。
具体的なオブジェクト
たとえばこれは明らかに具体物だ。
(defrecord AqoursMember [name blood-type birth-day])
だって AqoursMember と書いてある。
それが見たまんま ラブライブ サンシャイン に出てくるスクールアイドルを示す何かであることは疑いようもない。
データ
一方でそれは
IPersistentMap
だ。
それは key と value の対が収まった不変データそのもの。 歌ったり汗をかいたりはしない。
ただ assoc や map や reduce に渡せるインタフェースを満たすデータ構造だと考えることができる。
意味を忘れるとはつまり、それが僕達の仕事の中でどんな意味を持つかではなく、Clojureのプリミティブとして何であるかだけを考える、ということ。
データが何を意味するかは気にする必要ない。一般化して考えよう。
それがClojureにおけるボトムアッププログラミングのスタイルである、ということらしい。
現実的な問題に立ち向かう
そうは言っても僕達は具体物・具象から離れてはアプリケーションを作れない。 アプリケーションが特定の問題解くものである以上、絶対に避けられない。
そこで、Clojureのプログラミングではデータという抽象を扱うたくさんのAPIの 上に あるいは その外側 に領域特有(Domain Specific)のプログラムを構築する。
僕個人としてはこの考え方は結構衝撃的だった。
ドメインがいる場所
DDDを少しかじってみるとHexagonal Architectureというものに出くわす。
僕はアプリケーションの俯瞰図をそのイメージで考えることが多い。
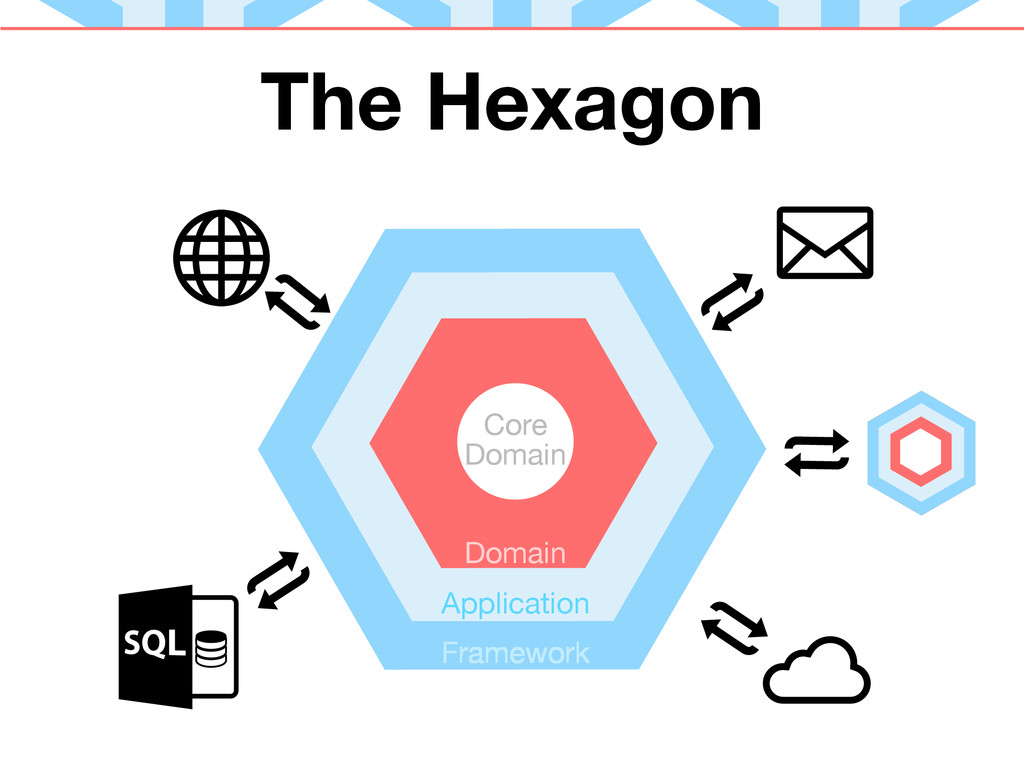
この図だと、ドメインつまり具体的なオブジェクトの集まりはアプリケーションの中核にいる。
でもClojureのワークフローに従うとこの中と外が 逆転 する。

ドメイン固有のオブジェクトは外側になる。
代わりに中核に居座るのは抽象データを操作する関数だけになる。
ボトムアップでコアを作っていく
ボトムアッププログラミングと口にする時、それはこの抽象データ用の中核を作っていくことに他ならない。
定義する関数が Person だとか AqoursMember だとか、そういうことは一切気にしないでプログラミングする。
勿論REPLでテストデータを渡すために仮のレコードを定義して使うことはあるかもしれないが、
呼び出される関数はそれらをただの Map として認識して操作する。
この一般化された関数を"ボトム"として、その上に少しずつ具体的な"トップ"を作っていく。
あるいは
この一般化された関数を"内側"として、その"外側"に少しずつ具体的なオブジェクトを作っていく。
まとめ
プログラミングClojureにおける"具体"と"データ"の違いを見てきた。
ボトムアッププログラミングとは、
- データを操作する関数を最初に作り、
- そこから具体的な意味を扱う関数をその上に作る
ようなワークフローである。
ということが解った。
謝辞
訳者の川合史朗さんの適切なアドバイスを受けてなんとかこの理解を得ることができました。 ありがとうございました。
ところで
原著の第三版 が出ている。
transducerとspecについての内容が追加されているらしく、もう原著で買うか、という気分になっている。
Left Recursionの悪夢再び
はじめに
Happyで生成したパーサのコンパイル遅すぎてもう限界だったのでparser combinatorに戻ってきた。
そしてまた現れたのだ、やつが。。。。
問題
やろうとしてることは以前と変わらない。
SML Definitionを読んで型の注釈を表す式 ty を解析しようとしているが、
左無限再帰が起きてしまって解析が終了しないというもの。
ty ::= tyvar (1) type variable such as 'a
{ tyrow i } (2) record type
tyseq longtycon (3) type constructor with type arguments
ty -> ty (4) function type
tyseq ::= ty (5) singleton
(6) empty
(ty1, ty2, ... tyn) (7) list of type
ここの (3) を解析する時にで遭遇するのがLeft Recursion(左再帰)問題。
ty という構文を解析する際に、(3)の type constructor のサブツリーを作ろうとする場合を考える。
この時、まずは tyseq を解析するステップに入る。
tyseq のEBNFを見ると明らかなようにこれは問題がある。
- (5) の場合は更に
tyに解析を開始するため左再帰が無限に下降する。 - (6) はmegaparsecの
optionを使えば表現できると思われる。 - (7) カンマ区切りの型のリストだが結局これも
tyの解析に入るので無限再帰する。
となるため確実に無限再帰に陥る。
よくブログ記事見かけるアドバイス
Text.Megaparsec.Exprを使えと言われる。
このモジュールは二項演算子や単項演算子で左再帰が発生する場合でも上手く取り扱ってくれる。
これを活用できないかと考えた。
-- ↓引数となる式 tyseq longtycon -- ↑後置単項演算子
こんな感じで捉える。
と思ったがこれを率直に実装するのは難しいと解った。 なぜなら型が合わないから。
このtype constructorの構文をADTのコンストラクタで表現するならこうなる。
TTyCon [Ty] TyCon
TyCon が後置演算子そのものを格納し、
[Ty] が先行する tyseq を格納する。
このコンストラクタの型は [Ty] -> TyCon -> Ty となる。
が前述のモジュールでは後置演算子になれるコンストラクタは Ty -> Ty である必要がある。
少なくとも手持ちのコンストラクタは [Ty] だがライブラリが期待するのは Ty なのでどうも合わない。
というところで今日は終了。
これから
いやー厳しい戦いだ。
あんまり基礎的なところが解っていないっぽいので異様に解決まで時間くうことが容易に想像できる。
GHCの中間言語Coreへの脱糖を覗き見る
Haskell (その3) Advent Calendar 2017 11日目の記事。(予約投稿知らなかったのでフライングになった)
GHCがコンパイルの途中で中間表現として用いるCoreの生成っぷりを観察する。
観察して、あーはいはいなるほどね(わかってない)、と言うだけになりそう。
はじめに
GHCはHaskellのソースコードを低レベルなコードへとコンパイルする過程で様々なpass(コンパイルのステージ)を通じてプログラムデータを変換する。 俯瞰図は下記のリンクに詳しい。
僕がGHCの話をどこかで聞きかじってかっこいいな、と思ったのは、 GHCがコンパイラの中間言語として定義しているCoreを知った時。
このCoreと名付けられた中間言語はDesugar passにて生成され、下記のような性質を持っている。
- 小さな構文
- 3つのデータ型と15の値コンストラクタ
- 束縛変数には全て型がついている
- 前段で推論されている
- 全て型がついているため高速に型検査ができる
- もう推論は終わっているので検査が高速
- 単純だが大きな表現力を持つ
GHCはリリースのたびに様々な言語拡張が増えていて、 表面上の構文は多様になってきている。 それにも関わらずこのCoreという中間言語は下記のような小ささを保っている。
- 3つのデータ型
- 15の値コンストラクタ
data Expr b = Var Id | Lit Literal | App (Expr b) (Arg b) | Lam b (Expr b) | Let (Bind b) (Expr b) | Case (Expr b) b Type [Alt b] | Cast (Expr b) Coercion | Tick (Tickish Id) (Expr b) | Type Type | Coercion Coercion deriving Data data AltCon = DataAlt DataCon | LitAlt Literal | DEFAULT deriving (Eq, Data) data Bind b = NonRec b (Expr b) | Rec [(b, (Expr b))] deriving Data type Arg b = Expr b type Alt b = (AltCon, [b], Expr b)
各値コンストラクタが依存している更に細かいデータ型はあるにせよ、 Haskellのソースコードは上記のデータ型にdesugar(脱糖)されて単純化される。
正直、僕もすべてのコンストラクタの意味が解っているわけではない。 しかしあの多彩な表現力を持ったHaskellの構文が この小さなCoreに変換可能である ことに大きく驚いた。
ここではこれらのデータ型の詳細には立ち入らず、 実際にHaskellのプログラム書きながらこのdesugarされたCoreがどう変化しているかを見てみようと思う。
観察してみる
この節ではGHCのデバッグオプションを使って、 parseされたプログラムがDesugar passを経た後の結果を確認してみる。
どんな感じで見えるんだろ。
Setup
stack.yamlにオプションをつけておこう。
ghc-options: "*": -ddump-to-file -ddump-ds -ddump-simpl -dsuppress-idinfo -dsuppress-coercions -dsuppress-uniques -dsuppress-module-prefixes
長い。長いけれどポイントは -ddump-ds のみ。
-dsuppres 系は冗長な出力を減らすために指定しているだけ。
このオプションをつけておくとstackのビルドの成果物を格納する .stack-work ディレクトリの下にレポートが出力される。
今回 src/Lib.hs に定義を書き下しているため出力結果は
.stack-work/dist/x86_64-linux-nix/Cabal-1.24.2.0/build/src/Lib.dump-ds
というファイルに出力される。
定数
stringConst :: String stringConst = "Hello"
-- RHS size: {terms: 2, types: 0, coercions: 0} stringConst :: String stringConst = unpackCString# "Hello"#
まあ、なんか、うん。そうだよね。
関数適用
falsy :: Bool falsy = not True
-- RHS size: {terms: 2, types: 0, coercions: 0} falsy :: Bool falsy = not True
変化なし。単純過ぎたか。
Infix
two :: Int two = 1 + 1
-- RHS size: {terms: 6, types: 1, coercions: 0} two :: Int two = + $fNumInt (I# 1#) (I# 1#)
なにか起きた。。。
二項演算子も結局は関数なので、
+ 1 1 のようなS式っぽい見た目になるのはわかる。
$fNumInt という謎のシンボルが出てきた。
後でも出てくるが型クラス Num の Int インスタンス定義を渡している模様。
関数合成
notNot :: Bool -> Bool notNot = not . not
-- RHS size: {terms: 3, types: 3, coercions: 0} notNot :: Bool -> Bool notNot = . @ Bool @ Bool @ Bool not not
x . y が . x y に変換された。
これもまた二項演算子が2引数の関数に変換されている。
だけではなくて @ Bool なる記号が出てくる。
これは . が持つ多相性に関連する。
次で説明。
多相関数
identity :: a -> a identity x = x
-- RHS size: {terms: 3, types: 3, coercions: 0} identity :: forall a. a -> a identity = \ (@ a) (x :: a) -> x
ちょっと形が変わった。大事なところにきた。
Haskellで匿名関数と作る時は
\ x -> x
とする。
なので
\ (x :: a) -> x
となるなら解る。 「aという型を持つxという値を受けとり、そのxを返す」というような意味で読める。
しかし実際は
\ (@ a) (x :: a) -> x
こう。
(@ a)
匿名関数に引数が増えている。
これは 型変数が関数の仮引数として定義されている ことを表す。
とても不思議。
-- 型 値 \ (@ a) (x :: a) -> x
型と値が同列の引数として扱われていることになる。
Coreでは型の引数と値の引数が同列に扱われて関数に適用される。
なのでこの関数に引数を適用する場合は、
identity Int 1
のようにして型引数が決定され、値引数が決定されているものと思われる。
補足: forall について
identity :: forall a. a -> a
forall が表れるが意味的にはもとの a -> a となんら変わらない。
糖衣構文として forall の省略が許容されていたものが、
脱糖を経て明示化されただけ。
補足: Core上の表現
この関数がCore上でどう表現されているかというと
Lam (TyVar "a") (Lam (Id "x") (Var (Id "x")))
ラムダ計算っぽく書くと
λ a. λ x: a. x
こんな感じ?
(解らないけど a にはkindとして * でもつくのかな?)
1つめのラムダ抽象の引数は型で、 2つめのラムダ抽象の引数はa型の値xとなる。
この2つの引数はCore言語内で Var という型を持つ。
型と値が同列で引数になる仕組みは簡単で、
関数の引数に束縛されるデータ型 Var が下記のようになっているから。
data Var = TyVar ... -- 型レベルの変数 | TcTyVar ... -- 不明 "Used for kind variables during inference" らしい | Id ... -- 値レベルの変数
この関数の引数に与えられるデータが
TyVar: 型Id: 値
どちらも受け付けるようになっている。
多相関数の適用 (型変数が決定されるのか?)
本当に型も引数として関数に適用されているのかを観察。 先程の多相関数に引数を適用してみる。
one :: Int one = identity 1
-- RHS size: {terms: 3, types: 1, coercions: 0} one :: Int one = identity @ Int (I# 1#)
予想通り。
@ Int で確かに型を適用している。
高階関数
おなじみの関数合成。
comp :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c comp f g x = f (g x)
-- RHS size: {terms: 9, types: 11, coercions: 0} comp :: forall b c a. (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c comp = \ (@ b) (@ c) (@ a) (f :: b -> c) (g :: a -> b) (x :: a) -> f (g x)
引数がお化け。。。。
だけれど、型変数の抽出ルールはやはり明確だ。
型変数は b c a の順で登場する。
それに合わせて forall b c a の順で定義される。
さらに forall に続く型変数はCoreのラムダ抽象で引数になる。
パターンマッチ
hasValue :: Maybe a -> Bool hasValue (Just _) = True hasValue Nothing = False
-- RHS size: {terms: 8, types: 7, coercions: 0} hasValue :: forall a. Maybe a -> Bool hasValue = \ (@ a) (ds :: Maybe a) -> case ds of _ { Nothing -> False; Just _ -> True }
関数定義部におけるパターンパッチはcase of構文に変換されている。
CoreのCaseコンストラクタに変換されているらしい。
Case (Expr b) b Type [Alt b]
実はこのコンストラクタ b と Type の部分がまだ何者か判明していない。
b が Expr b を束縛しており、 Type が [Alt b] の式の型を注釈している?
型クラス制約
型クラスつきの関数を定義するとどうなるだろうか。
join :: (Monad m) => m (m a) -> m a join = (>>= id)
-- RHS size: {terms: 8, types: 17, coercions: 0} join :: forall (m :: * -> *) a. Monad m => m (m a) -> m a join = \ (@ (m :: * -> *)) (@ a) ($dMonad :: Monad m) (ds :: m (m a)) -> >>= @ m $dMonad @ (m a) @ a ds (id @ (m a))
斬新な変数が出てきた。 引数部分を分解して一つ一つ読み解こう。
(@ (m :: * -> *)) -- Monadのインスタンスとなるべき型 (@ a) -- mで修飾された入力値の型の一部 ($dMonad :: Monad m) -- 型クラスを満たすインスタンスの定義 (ds :: m (m a)) -- 実際の関数の入力値
join に表れる型変数は m と a 。
なのでその2つは最初に (@ (m :: * -> *)) と @ a として束縛される。
(ds :: m (m a)) は実際の関数の引数なので疑問なし。
問題は ($dMonad :: Monad m) というどこから出てきたのか解らない束縛。
これは型クラスのインスタンスも関数の引数として受け取るための束縛らしい。
ということは、型クラスのインスタンスを渡しているところも見られるかもしれない。。。
型クラスのインスタンス適用
さきほど定義した join を使ってみよう。
maybeOne :: Maybe Int maybeOne = join (Just (Just 1))
-- RHS size: {terms: 6, types: 5, coercions: 0} maybeOne :: Maybe Int maybeOne = join -- (@ (m :: * -> *)) @ Maybe -- (@ a) @ Int -- ($dMonad :: Monad m) $fMonadMaybe -- (ds :: m (m a)) (Just @ (Maybe Int) (Just @ Int (I# 1#)))
コメントで先程の join の定義と対照してみた。
Monad のインスタンス定義を受け取る部分には
$fMonadMaybe
が。
名前から察するにどうやらMaybeのインスタンス定義が渡されているようだ。 (Scalaが型クラスのインスタンスとしてimplicitパラメータで渡しているものと、ほぼ同じものだと思われる。)
Monad
最後にモナドを含むdo記法がどのようにCoreに変換されるのかを見てみる。
printArgs :: IO () printArgs = do args <- System.Environment.getArgs print args
-- RHS size: {terms: 7, types: 8, coercions: 0} printArgs :: IO () printArgs = >>= @ IO $fMonadIO @ [String] @ () getArgs (\ (args :: [String]) -> print @ [String] $dShow args)
doは糖衣構文なので脱糖後は >>= を使った式に変換されるのは予想できた。
型周りは思ったよりいろいろ混ざってきて混乱。 上から見ていく。
bind関数の定義。(型制約は除く)
>>= :: m a -> (a -> m b) -> m b
これは forall つきで表現すると
>>= :: forall m a b. m a -> (a -> m b) -> m b
となる。
よって
(@ (m :: * -> *)) (@ a) (@ b)
が型変数として関数の引数に抽出される。 実際の対応をみてみると
-- (@ (m :: * -> *)) @ IO -- ここはMonadのインスタンスとしてIOの定義を渡している $fMonadIO -- (@ a) @ [String] -- (@ b) @ ()
これらを使うと >>= は下記のように具象化される。
-- getArgsより printより >>= :: IO [String] -> ([String] -> IO ()) -> IO ()
型変数だった部分全てに具体的な型が当てはまった。
まとめ
Haskellのプログラムはdesugar(脱糖)後にCoreという中間言語に変換される。
Coreは基本的に型付きラムダ計算(の変種)なので
- 変数
- 関数の定義
- 関数の適用
- その他 Let, Case ...
などのわずかな定義で構成される。
さらに値と型が同レベルで束縛されるラムダ抽象を用いることで
- 型クラスのインスタンス渡し
- 具象型の決定
などの操作が ただの関数適用 で実現されている。
少ない規則で多彩なユースケースを実現している好例がGHCの中に潜んでいることを知ることができてよかった。
Less is more.
Yoshiko is Yohane.
Reference
- Simon Peyton Jones Into The Core
- GHC Compiler pass
- CoreのAPI Document in GHC 8.2.2
- GHCのデバッグオプション
- GHCにおける多彩な情報の出力方法
- もっと踏み込んだ解析 Dive into GHC: Targeting Core
- この記事よりもちゃんと調べている: GHC Core by example, episode 1: Hello, Core!
下記、余談
モチベーション
Haskell Day 2016が日本で開催された時にSimon Peyton Jonesさんが"Into the Core"というタイトルでプレゼンされたらしい。 残念ながら僕は都合がつかず聞きにいけなかったけれど、同じテーマの講演が動画に収められていたのでそれをリンクしておく。
Into the Core - Squeezing Haskell into Nine Constructors by Simon Peyton Jones
早口過ぎて99%何を言っているのか僕には解らない。 けれどところどころなんとなく伝わる気がする。
プレゼンで使ったスライドは こちら
これをぼんやり聞いていて「Coreってなんだか面白いな」と思ったのがきっかけ。
これから
Coreの理論的背景になっているSystemFというラムダ計算の一種が何者なのか気になる。
GHCで用いられているSystemFCという変種については下記のリンクが参考になりそうだけど。
System F with type equality coercions
僕はそもそもラムダ計算素人なので下記の書籍を読み進める必要がありそう。
最短で
- 3章: 型無し算術式
- 8章: 型付き算術式
- 9章: 単純型付きラムダ計算
- 23章: 全称型
を読めば辿り着けるように見える。
いやーほんとかなあ。。。
SMLの関数適用を構文解析する時の問題
まだ構文解析器で苦労している。 今回も詰まっているのは構文のconflict。
問題
これが関数適用
app : exp exp
これが二項演算子適用
infixapp : exp vid exp
この時に入力を
x y z
とすると2つの解釈ができてしまうことになる。
((x y) z)
とするネストした関数適用なのか
x y z
とする二項演算子の適用なのかParserが判断つけられない。
前者ならreduceするが後者ならshiftする。 なのでこれはshift/reduce conflictが起きていると言える。 happyはデフォルトでshiftするので二項演算子として解釈される。
これを解消したい。
解決
sml-njやmltonのgrmファイルの定義を覗いたところ
FlatAppExp : exp list
のようなデータコンストラクタを使ってとりあえずシンボルのリストとしていったん読み込んでしまうらしい。 なぜ関数適用と二項演算子適用は全然違う構造にも関わらず峻別せずに扱うのだろうと疑問に思った。
なぜだろう
SMLではfixityを自分で定義して二項演算子を作れる。
左結合か右結合かをどこかのテーブルに保存しておくことになる。(おそらくEnv的なもの?まだそのあたり解らない) こういう動的にassociativityが定義される二項演算子はパーサジェネレータでは扱えないっぽい。
なので一度解析しきってから、後でsanityチェックして弾くっぽい。
解析の途中でこのfixityのテーブルを更新しながら進めば別に解析の完了を待たなくてもいいじゃんとも思った。 けれど、それだとfixityの定義が必ず演算子の使用よりも前に定義済みである必要がある。 それは不便だろう。
ということでFlatなんたらという構造を導入してなんとか解決はできた。
追記
http://dev.stephendiehl.com/fun/008_extended_parser.html
ここを見るとinfix operatorを動的に定義していく方法が提示されているが、やはりparsecだな。ghcはどうやっているのか見てみる必要ありかな。。。
納得いってない
悪手かなと思うのは、こうした構文解析上の問題のために抽象的なデータ構造にコンストラクタを追加しなければならないという点。 せっかくきれいにsyntax objectを定義できたのにノイズが入ってしまうみたいでイマイチだなと思う。
これだと
1 + 2 + 3
みたいな入力は
[ "1", "+", "2", "+", "3" ]
のようにreduceされる。
parsecならこれをexpression builder的なAPIでうまく木構造に変換できるのだが。。。 まあ、部分的にparsec使うのはありかもしれない。
これから
あとはモジュール系の構文解析が作れればとりあえず構文解析のステージは終わりだろう。 と、言いたいところだがshift/reduceやreduce/reduceのconflictがわんさか残っている。
どうしよう。。。問題ないならこのまま進めてしまいたい。 正直conflictの解消法は未だにわかってない。
あとまだわかってないこと。
- 構文解析終わった後のsyntax objectに位置情報を顕に保存していないけれどtype checkエラーの時に位置情報含めてレポートできるのか?
- そもそもエラーレポートがすごくわかりにくい。後で苦労するので早めにverboseなレポート出せるようにしたい。
やりながら良かったと思うこと。
- haskellのhappy使ってるけどmlyaccやyaccととても似ているため他のツールチェイン使った時もこのノウハウは活きるだろう
- テストはこまめに書いているので「ここまでは動く」という証左が得られる安心感はやっぱり良い。プログラマとしてこの感覚は大事にしたい。
その他近況メモ(ぼやき)
カーネル
詳解Linuxカーネル読んでる。 メモリアドレッシングからいきなりハードル高い。
特にページングテーブルの初期化のところとか全然解らない。
Clojure
Scala勉強しなきゃ、からマッハで脱線してClojureの情報ばかり漁っている。
どっかの記事で「Clojureは大規模プロジェクトになるとメンテナンスが難しくなってきてスケールしない」みたいなこと言ってた。 そうだろうなと思う。 リファクタリングはそれほど気軽にできないだろう。
specが出てきてチェック機構は揃ってきているけれど、 それでもやはり「実行しないと結果が解らない」という制約は残る。
REPLで探索しながら直すべきところは見つけられるよ、という意見もあるかもしれないけれど リファクタリングの過程で影響のあるところ全部を検査する仕組みはやっぱり無いではなかろうか。 というかリファクタリングして壊れたところを機械的に見つける手段が無い、と言うべきか。
Clojureもそうだけど、RubyやPythonやJS使っている人たちどうしているのだろう。素朴に疑問。
とかぐだぐだ言いながらもなんかClojure好きなので勉強を続けてしまう。
好きなプログラミング言語の好きなところについて思った
改めて最近実感すること。
Haskell, Elm, Clojureほんと好き。
Scala勉強しなきゃなーと思いながらClojureを触ってしまうことが多かったのだけれど、 その理由が少しずつわかってきた。
いい言語たち
いままで少しだけ触れてきたJava, Python, Scala, Goはいずれもとても大きなユーザを抱えている。 どの言語もたくさんのユーザを得るために現場で使えるようなエコシステムをどんどん投下してあっという間に大きなユーザベースを獲得した。
プログラミングのしやすさを大事にして、誰でもすんなり入門できるように設計されている。 僕が入門できるくらいだから本当に敷居が低くて、けれどどんなやりたいことも実現させてくれるいい言語ばかりだ。 押し付けがましい思想も少ない。
たのしい言語たち
一方でHaskell, Elm, Clojureはちょっと独特だ。
HaskellではMonadicなプログラミングやSTM, デフォルト遅延評価など今まで触れたこともないようなパラダイムで溢れていた。
ElmではElm Architectureという一見してみると強い制約のもとでWeb UIを構築しなければいけなかった。
ClojureではREPL駆動開発やtransducer, 状態のオペレーション(STM, Atom, Agentなど)という独特なキーワードが骨子になっている。
(あ、全部関数型プログラミングだ。。。)
いずれも今までの自分には聞いたこともないような概念ばかりで、きっと解らなくてすぐに挫折してしまうだろうと思った。 だけど全然そんなことはなかった。むしろ楽しかった。
やりたいことが手元にあって、それを実現するためにどうしようかと考える時、Haskell, Elm, Clojureではまず素直に落とし込めない。 どんなやり方があるのか調べて、どれがその言語らしい XXX way なのかを知っていかなければいけない。 本当に手間がかかることが多い。
なのになんでこんな楽しいのだろう。進まない。進まないのに。
簡単≠たのしい
その制約のせいか、「できた!」と思った時の瞬間が本当に嬉しい。やっていることは全然大したことない。 SpringBootとかDjangoとか使えば瞬殺なのだろう。
でも、なんというか、その言語の思想に沿うように実装できた時の嬉しさは要求を鮮やかに実現できた時の歓喜とは別の何かだ。 3Dプリンターで模型を切り出すのではなくて、彫刻刀で大仏を彫り出すような変なドグマの混じったカタルシスを感じる。
何ができるかではなくて、どうやるかが楽しい。 ほんと、仕事としてプログラマやっている人間としては全然駄目だと思う。 実際問題、顧客の要求を低コストで十分に実装する能力や判断力の方が絶対にお金は入るはずなんだ。 成果物や収益から逸脱して、作法や流儀や過程に楽しみを見出してコストを支払うなんて多分駄目なはずなんだ。
でも何故だろうか、遠回りなのに美しい道が用意されているように見えるプログラミング言語ばかり好きになってしまう。 マーケットとか人材の需要とかじゃなくて、思想や信念や流儀に見え隠れする怪しさ(妖しさ?)に惹かれてしまう。
本当はScalaやPythonやGoに触れて経験を積んだ方がきっとすぐに応用に入れる場面も多いはずなのに。 どうもそういう打算が働かず、ただただ楽しいと思うプログラミング言語に傾倒していくのを自ら止められずうろうろしている。
幸い、Haskell, Elm, Clojureはプロダクションでの採用事例も増えてきている。いずれ自分が書いたHaskell, Elm, Clojureのコードがプロダクション環境で動く日が来たらいいなあ、と思う。
Erlangとかもなんだか光背が見える言語だ。。。気になる。
ネットワーク機器の制御とかでHaskell, Elm, Clojureあたり使っている会社の仕事とかあったらいいなー。 ネットワーク(特にバックボーン)業界はだいたいPythonかJava, Goなのでもう少し僕が好きなプログラミング言語の実装増えてこないかなあ。
(自分で書いていけってことか。。。)
技術書を読む時の問題意識について(答えはまだない)
何か学習したい、と思う動機があるとする。
現在の僕の場合は「仕事の関係でLinuxカーネルについておさえておきたい」とか。
学習したいので何らかの書籍を参照することになる。
問題
読んでいる内容が頭に定着していない感覚
購入した詳解Linuxカーネルでは「メモリアドレッシング」の章で、 ハードウェアの仕様も含めて、章タイトルについての詳細な説明がなされている。
どうもこれを読んで頭に入っていると感じない。
そもそもセグメンテーションて何だ、というのがわからない状態で読み出す。
何故か
そもそもメモリアドレッシングについての問題意識がない。 気にしたことがないし、それについて知りたいと思うような動機づけの体験がない。
なので読んだところで「読まされている」状態から抜け出せない。
逆説的に、メモリアドレッシングにまつわる問題に過去出会っていて、 どうしても詳細まで掘り下げたかった人はよく頭に入ることだろう。
書籍を読んでいて「なるほど」と思うには、 まずそれを解きたいと思うなりに本人の中に謎みたいなものが定着している必要がある。 これまでの体験により伏線だけが溜まっている状態だ。
書籍を読むことで体験した事実に対する説明がなされて、 伏線回収がおこなわれる。 この時に初めて「なるほど」と納得する。
僕が頭に定着する、と言っているのはこの変化のことを指す。
つまり、僕は伏線を持たずに伏線回収の説明をされている状態なわけだ。
どうしたらいいのか
2つくらい思いついた。
1. 愚直にわからないところを調べる
読み進めるにあたって解らないところを新しく問題意識の対象と捉えて解きにかかる、という考え方。
Intelのアーキテクチャまで知らないとだめなのでは。 いったいどこまで深く潜ったらいいのだろう。
DMACも調べないといけない。
足元に広がるハードウェアの世界は広すぎて探索の意欲が減っていきそうだ。
2. 解ったことを整理して解らなかったところを記録する
たぶん現実的な解法。
「あとでがんばる」という判断で不明なところを棚上げにして進む。
詳解Linuxカーネルは頭から読んでいくような章立てに必ずしもなっていないし、 これからも細部でわからないところが想像以上に出てくるだろう。
これにいちいち付き合って深堀していると前進感も得られないし、 きっとどこかで挫折するだろう。
シナリオを進めるためにはいったん「逃げる」コマンドを使うことも必要だということかな。
大事なのはあとで「戻ってくる」ことだけれど、うーん、戻ってくる気が起きるかどうか。。。。
まとめ
書籍を読んで納得するには、知りたい問題が頭の中に既に用意されている方が良い。
といっても書籍に書いてあること全てに対して問題意識を持っているということはまず無い。
なので納得に至らないなら、一度進んでまた戻ってくる方が精神衛生に良さそう。
結城浩さんの数学ガールは問題意識の発露からストーリーに乗せて語るので、読者が露頭に迷うことが少ないのかな、と脱線しながら思った。
小さく作ることとモチベーション
Minimum viable product - Wikipedia
小さく作りながら進めるのがうまい人は作業ステップの分割ではなくてゴールの分割に優れているなあ、と思う。 最低限のユーザが試すことができる機能のみを搭載したプロダクトをMVP(Minimum Viable Product)というらしい。
僕が実例で見て痛感したのはRui Ueyamaさんの動画。
小さいけれど動くものを作る。 できたものをテストして、また機能をリッチにしていく。
Rebuild.fm #153にUeyamaさんが出ていた回では「インクリメンタル」と表現していたアプローチ。
なんでこれが良いのか
僕自身のモチベーションが維持できる。 小さくてもフィードバックが得られるから。
小さくても動くという達成感がいかに大きいか、最近Haskellでコード書いていてつくづく思う。 少し書いたら小さなテストを作って確認していく。
「ここまでは動きそうだな」というのが安心感として得られる。
安心!
安心が大事だ。モチベーションは精神性に根ざすので、安心という心の状態がモチベーションに寄与するのは、なんとなくreasonableな気がする。
安心して進めたい。うんうんと頷きながら進めたい。わけがわからなくなって疲れて飽きてやめたくない。
そのためにゴールを小さく分割して作っていこうよ、という活動が僕なりのMVPの効用だ。
はまりがちなこと
頭にあるものを一気に吐き出そうとすると、前述の進め方を忘れてしまうことがある。
とにかく全部一度作りきろうとするのだ。
すると一気に作ったあと一気に動作を検証していくことになる。 一気に作ったものがきれいに動作することは大抵なくて、長いデバッグが始まることを意味する。
フィードバックを得る機会は先延ばしになり、モチベーションは消費されるだけになってくる。
今度はだんだんデバッグが辛くなってきて腰が重くなってくる。 こうなるともう赤信号だ。
今までこういう隘路にはまって続かないことが多かった。
小さくゴールを分割するということ
これは難しい課題だ。
問題領域がよく解っているならゴールの分割はわけないだろう。 でもインクリメンタルにモノを作っていく時、大概の場合は作ろうとしているモノの全体像はわからない。 自然と探索的にゴールを切り取っていくことになる。
これに定石があるようには思えない。なので都度頭を悩ませながらゴールを切り取っていくのだろう。
けれど、間違った判断をしていることに気づけるかもしれない。 例えば、ゴールを分割するのではなく、作業工程を分割するような間違いだ。 ユーザーストーリーマッピングの本では、とても大きなケーキを作る作業を例えにだしていた。
ゴールを小さく区切るMVPの考え方に従うと、小さなゴールとは例えば1/16くらいのサイズのカップケーキのようなものだという。
誤った分割をしている場合は、大きなスポンジを作ることだという。
大きなケーキを工程で分割してしまうと後者の過ちを踏むことになる。 対照的にMVPに従ってゴールを分割すると、前者のように小さいけれどユーザにデリバリできる単位が成果になる。
フィードバックを得やすいのは明らかに前者、ということだ。大きなスポンジだけ渡されても、それはケーキではないから誰も評価できない。 一方小さなケーキは小さくてもケーキだ。食べてケーキとしての出来栄えの感想を述べることができる。
幸いにしてソフトウェアは小さな部品を合成して大きな部品を構築できる性質を備えている。 小さなケーキを合成すると大きなケーキが作れる。
これを利用しない手はない、ということらしい。
まとめ
小さいけれど充分に動作する機能を反復的に作っていく。 これはモチベーションを維持していくことにとても効果がありそうだと思った。
もちろん難しいのはゴールの分割する思考法だ。
それでも三日坊主になりがちな僕でもモノを作り続けられるかもしれない唯一のアプローチではないかと思っている。